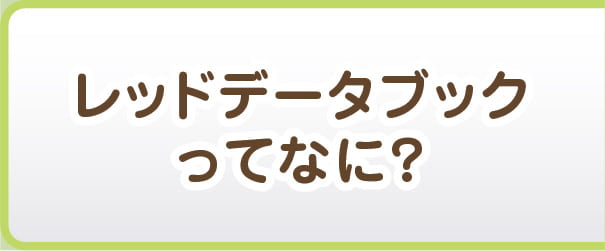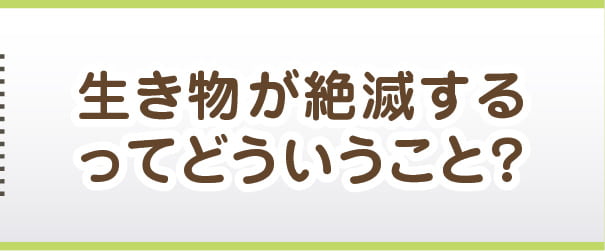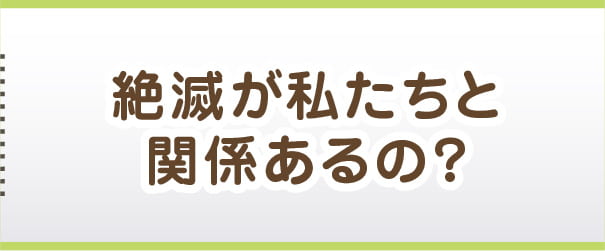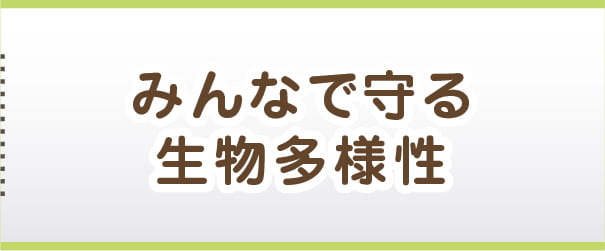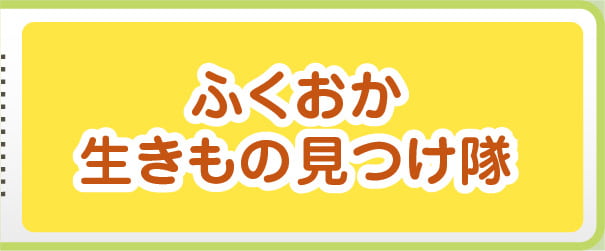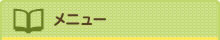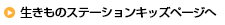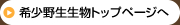希少な生きものとたくさん会えるところは?①
里山(さとやま)がそのひとつです。
里山とは、人が炭(すみ)やたきぎ、畑の肥料(ひりょう)となる落ち葉などをとるために整備(せいび)した雑木林(ぞうきばやし)、農業をするために作った田畑や水路、ため池、人がくらす集落などが組み合わさって一体になった地域(ちいき)のことです。
日本は梅雨や台風など雨が多い国なので、季節によって川の水量が変わったり、時々洪水(こうずい)が起こったり、山の斜面(しゃめん)がくずれたりしていました。日本には、こうした定期的な環境(かんきょう)の変化を好む生きものが多くくらしていたので、人が定期的に手を加えて作ってきた里山は、このような生きものの大切なすみかになっていました。
でも、今は里山にすむ人が少なくなってしまったので、里山が管理されず環境(かんきょう)が荒(あ)れてしまった場所が多くあります。その結果、里山をすみかにしていた多くの生きものが、絶滅(ぜつめつ)の危険性(きけんせい)が高まってしまったのです。
よく管理された里山には、今もトノサマガエルやアカハライモリ、ミナミメダカ、ゲンゴロウ類、キンランやキキョウなど、たくさんの希少な生きものがくらしています。