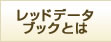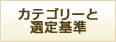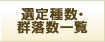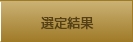植物等・動物
■選定結果の概要
- (1)掲載種数
今回の見直しの結果,福岡県レッドデータブック2024における掲載種(亜種,変種を含む)は,全分類群合計で1,811種となった(表6)。その内訳は,絶滅(EX)67種,野生絶滅(EW)2種,絶滅危惧ⅠA類(CR)347種,絶滅危惧ⅠB類(EN)360種,絶滅危惧II類(VU)376種,準絶滅危惧(NT)400種,情報不足(DD)259種であり,絶滅危惧種(CR,EN,VUの合計)として1,083種が掲載された。福岡県レッドデータブック2011・2014における掲載種数は1,611種であり,今回は,そのうち1,516種が再選定,95種がカテゴリー外として評価された。一方,新規に295種が掲載されたため,掲載種数は,差し引き200種の増加となった。
- (2)新規絶滅種・新規掲載種
絶滅67種のうち,ヒメノボタン,ギボウシランなど植物12種,ゲンゴロウ,ダイコクコガネなど昆虫類11種について,今回,新たに絶滅が確認されたものとして掲載された。福岡県レッドデータブック2011・2014では絶滅種は53種で,そのうち9種が今回再発見などにより下位のカテゴリーに移行されたため,絶滅種の種数は,差し引き14種の増加となった。
掲載種数が多い分類群における新規の掲載種は,種子植物ではコバノヒルムシロ,キンセイラン,カワラマンネングサなど60種,シダ植物ではクマイワヘゴなど17種,鳥類ではオバシギ,チゴモズなど37種,魚類ではシラウオ,アイナメなど36種,昆虫類ではニセコウベツブゲンゴロウ,ウスバカマキリ,アキアカネなど62種,甲殻類等ではアナジャコウロコムシ,チスイビルなど29種であった。
- (3)各分類群における掲載種数の増減傾向
掲載種の増加割合が比較的高かった分類群は,藻類(2011:11種→2024:17種,1.55倍),菌類(2011:6種→2024:24種,4.00倍),鳥類(2011:90種→2024:119種,1.32倍),魚類(2014:82種→2024:109種,1.33倍)甲殻類等(2014:45種→2024:73種,1.62倍)などであった。いずれの分類群においても,これまで評価のための情報が不足していた対象種について,現地調査や文献などにより分布情報や生息状況などのデータが蓄積され,それに基づき評価が行われたことが主な理由である。また,今回,掲載種数が200種増加したのにもかかわらず,絶滅危惧ⅠA類(CR)の種数が約20種減少した。その主な理由は,種子植物についても定量的データが蓄積され,それに基づく再評価が行われた結果,前回は絶滅危惧IA類(CR)であった種のうち,より下位のカテゴリーに移行されたものが61種あったことによる。
■絶滅危惧種の危機要因
全分類群の絶滅危惧種(1,083種)おける危機要因として,最も多かった項目は,産地局限:360種であり,次いで水質汚濁:249種,遷移進行:243種,森林伐採:234種,海岸開発210種の順であった(図1)
- (1)産地局限
産地局限は,種子植物,貝類,昆虫類などの危機要因として比較的上位に挙げられ,自然状態での生息地がもともと局所的で生息個体数も少ない種などが該当した。
- (2)水質汚濁
水質汚濁は,貝類,水生昆虫類,甲殻類などの主要な要因として挙げられており,これらの生物の生息地である水域環境の悪化およびその懸念を反映している。
- (3)遷移進行
遷移進行は,種子植物の主要な要因として挙げられており,遷移進行による二次草原や二次林などの二次的自然の縮小・消失がこれらの植物の存続に大きな影響を与えている。
- (4)開発行為に関する危機要因
森林伐採,海岸開発などの開発行為に関する危機要因は,河川開発,湿地開発,ため池改修なども含めて,各分類群の生息環境に応じた個別要因として挙げられており,開発行為による生息地の改変・消失は,依然として大きな危機要因となっている。
- (5)シカ増加・園芸採取
また,今回,シカ増加が107種で挙げられ,種子植物やシダ植物の摂食という直接的影響のほか,昆虫類などの生息環境の悪化という間接的影響も生じていると考えられる。このほか,種子植物では園芸採取が130種で挙げられており,特に園芸的価値の高いラン科植物などの盗掘被害が各地で生じている。
■掲載種のIUCNレッドリストカテゴリー
今回,全掲載種について環境省レッドリスト2020における評価結果に加えて,IUCNレッドリストにおける評価結果についても巻末の福岡県レッドリスト2024に記載した。IUCNレッドリストで未評価(NE)とされた種は1,427種あり,全掲載種の79%を占めた。また,低懸念(LC,絶滅危惧基準の要件を満たしていないもの)が284種で全掲載種の16%,評価された種(384種)のうちの74%を占めた。分類群別に見ると,哺乳類,鳥類,爬虫類,両生類,魚類の掲載種では,半数以上の種が評価されていた。一方,種子植物,シダ植物,蘚苔類,藻類,地衣類,菌類,昆虫類,甲殻類等,クモ形類等,貝類では8割以上の種が未評価であった。未評価の種には,日本固有種や日本とその周辺のみに生息する種が多く含まれ,また,評価された種についても分布情報や生息状況が評価者に十分に認識されていないことも考えられるので,IUCNが独自に評価した結果であることに留意が必要である。