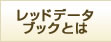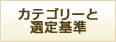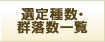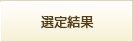-
(1)地形
福岡県は九州の北東端に位置し,その県土面積は約4,990km2で,国土面積の約1.3%を占めている。北側は筑前海(玄界灘,響灘),東側は豊前海(周防灘),南西側は有明海に面しており,西の佐賀県とは東西に延びた背振山地および筑後川が,南東の大分県とは英彦山地および山国川が,南の熊本県とは釈迦岳山地および諏訪川(関川)が,それぞれ境界となっている(図2)。
県域は地形的に大きく4つの流域圏に区分され,福智山地(福智山901m)・英彦山地(英彦山1,199m)に挟まれ今川・祓川などを主要な流域とし東側に開けた京都平野,福智山地・英彦山地・三郡山地(三郡山936m)に挟まれ遠賀川などを主要な流域とし北側に開けた筑豊平野,三郡山地・背振山地(背振山1,055m)に挟まれ那珂川・室見川などを主要な流域とし北側に開けた福岡平野,三郡山地・古処山地(古処山860m)・釈迦岳山地(釈迦岳1,230m)に挟まれ筑後川・矢部川などを主要な流域とし西側に開けた筑後平野という地形的特徴を有している。森林面積は約2,250km2で,人工林の割合が約6割と高い。このうち,英彦山地や釈迦岳山地などの自然林,平尾台の草原,豊前地域や北九州市若松区・福津市・古賀市などのため池群,有明海側の農業水路群,筑前海沿岸域の岩礁や砂浜,豊前海・有明海沿岸域の大規模な干潟は,本県を特徴づける重要な自然環境として挙げられる。 -
(2)気候
福岡県の気候は年間を通すと温暖的要素が強いものの,日本海側に位置する福岡・北九州地方は冬季には大陸からの寒気の影響を受け,日本海側気候区の特徴を示す。筑後平野を中心とする内陸平野部は三方を山に囲まれており,内陸型気候の特徴を示し,筑豊盆地は,気温の日較差や年較差が大きく,盆地特有の気候を示す。降水量は県内全域でおおむね年間1,600mm以上となっており,県境山地では2,400mmに達する場所も知られる。
-
(3)生物相
福岡県は九州最北部で本州と中国大陸の中間に位置することから,その生物相は両地域の要素を併せ持つ独特なものとなっている。大陸に近いという地理的条件により,多くの渡り鳥の越冬地・中継地として重要な役割を果たしている他,過去の氷期における海水面低下時の水系接続の地史を反映して,県東部の生物相は本州・四国の瀬戸内海側の地域と関係が深く,一方で県西部の生物相は朝鮮半島や中国大陸と関係が深い。特に西部では有明海を中心に,シチメンソウやムツゴロウ,ハラグクレチゴガニなどの大陸系遺存種と呼ばれる中国大陸・朝鮮半島と共通する生物が自然分布することは特筆すべき点である。また,福岡県の固有種・亜種としては魚類のハカタスジシマドジョウ,オンガスジシマドジョウ,貝類のミヤザキムシオイが知られる。この他,当県と周辺地域にのみ分布する固有性の高い種として,藍藻類のスイゼンジノリ,両生類のカスミサンショウウオ,チクシブチサンショウウオ,魚類のセボシタビラ,アリアケスジシマドジョウ,アリアケヒメシラウオ,貝類のキュウシュウササノハガイなどが挙げられる。
県域における生物の重要な生育・生息環境(ハビタット)を大きく区分すると,①山地森林,②低地森林,③草原,④河川,⑤湿原・池,⑥水田・水路,⑦河口・干潟,⑧海岸,⑨海域,⑩その他の10の類型を挙げることができる。以下にその概要と生物相の特徴をまとめる。
- ①山地森林はおおむね標高700~800m以上の夏緑樹林で,県内では標高1,000mをこえる英彦山地や釈迦岳山地などにみられる。植物,哺乳類,鳥類,昆虫類,クモ形類等の重要なハビタットである。
- ②低地森林はおおむね標高500m以下の照葉樹林や雑木林で,山地の他に丘陵地や平地,農地にみられる。植物,哺乳類,鳥類,爬虫類,両生類,昆虫類,クモ形類等,貝類などの重要なハビタットである。
- ③草原は県内では平尾台が代表的なもので,一部河川敷などにもみられる。草原性の植物や昆虫類などにとって重要なハビタットである。
- ④河川は県内では筑後川,矢部川,遠賀川を代表として200以上の水系がみられ,魚類を中心に水生の植物,鳥類,両生類,昆虫類,甲殻類等,貝類などの重要なハビタットである。
- ⑤湿原・池は県内では農業用ため池を中心とした二次的な環境が主で,豊前地域や響灘・玄界灘に面した農地や農地の後背の中山間地に多くみられる。水生の植物,鳥類,両生類,魚類,昆虫類,甲殻類等などの重要なハビタットである。
- ⑥水田・水路は全県的にみられるが,特に有明海に面した地域の農地にある掘割(クリーク)群は特徴的である。魚類を中心に水生の植物,鳥類,両生類,昆虫類,甲殻類等,貝類などにとって重要なハビタットである。
- ⑦河口・干潟は河川と海の合流部や前浜部にみられ,県域は一般的に干満差が大きいことから特に干潟がよく発達する傾向にある。鳥類,魚類,甲殻類等,貝類などにとって重要である。
- ⑧海岸は岩礁や砂浜を代表とし,響灘・玄界灘側に多くみられる。植物(藻類),鳥類,昆虫類,貝類などにとって重要なハビタットである。
- ⑨海域は瀬戸内海(周防灘),日本海(響灘・玄界灘),有明海と異なる3つの異なる海域があり,それぞれ異なる特徴をもつ。鳥類,魚類,甲殻類等,貝類,一部の哺乳類にとって重要なハビタットである。
- ⑩その他については石灰岩地帯や洞窟が挙げられ,一部の植物,昆虫類,貝類などにとって重要なハビタットである。