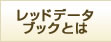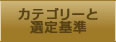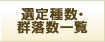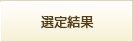はじめに
私たち日本人は、戦後の高度経済成長を通じて経済大国となりましたが、その一方で国土は開発によって大きく変貌しました。その過程で、かつては私たちのまわりにふつうにみられた生き物が、姿を消していきました。福岡県でも、メダカやトノサマガエル、ヘイケボタルやニホンイシガメなど、かつての普通種が今や希少種となっています。このような種の減少は、伝統的な農村景観の消失や里山の荒廃とともに生じている変化です。いわば、子供のころに慣れ親しんだ「ふるさとの自然」が失われるなかで、多くの生き物も姿を消しています。一方で、イノシシやキュウシュウジカなど、かつては狩猟によって低密度に抑えられていた動物が急増し、農林業被害を発生させるとともに、森林の林床植生を消失させ、希少種を含む他の動植物の生息地を消失させています。
同様な変化が世界中で起きており、「生物多様性損失」として国際問題となっています。このため、2010年に名古屋で開催された生物多様性条約第10回締約国会議では、「自然共生社会」(Society in harmony with nature)という日本が提案した社会像が、国際的に支持され、そのモデルとしてSatoyamaという日本語が国際的に注目を集めています。また、2022年に開催された生物多様性条約第15回締約国会議では、「昆明・モントリオール生物多様性枠組」において2030年までの新たな国際目標が合意され、「自然共生社会」というビジョンを引き継いだ「ネイチャーポジティブ」な社会を実現するために、世界各国でさまざまな努力が続けられています。
このような状況を背景として、福岡県では「福岡県レッドデータブック2011」「福岡県レッドデータブック2014」を出版し、絶滅のおそれのある植物群落・生物種を選定して、その保全の重要性を指摘しました。今回出版するのはこれらを改訂した最新版であり、最新の調査結果にもとづいて絶滅のおそれのある種を選定したものです。本書をもとに、これらの種の保全に寄与し、さらにこれらの種の生息場所となっている森林や湿地などの生態系の保全に寄与する対策を進める必要があります。また、これらの種や生態系の保全をめざす県民の取組みがさらに活発なものとなることを期待します。
会長 矢原 徹一