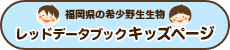チャレンジクイズ
- トップ
- チャレンジクイズ
生物多様性(せいぶつたようせい)についてクイズにチャレンジしてみよう!
生物多様性(せいぶつたようせい)について知っているかな?学んだかな?まだまだ知らないことがあるかもしれない!
ここにはいろいろなクイズがあるので、友だちや先生、保護者(ほごしゃ)やきょうだいとクイズを出しあってみよう!

福岡県で一番高い山はどれでしょう生物多様性(せいぶつたようせい)
A釈迦岳(しゃかだけ)

八女市と大分県日田市の県境(けんきょう)にある釈迦岳(しゃかだけ)(標高1230m)が一番高い山です。次いで、御前岳(ごぜんだけ)(1209m)、英彦山(ひこさん)(1199m)、犬ヶ岳(いぬがたけ)(1131m)、脊振山(せふりさん)(1055m)が続きます。
福岡県で最も西に位置する島はどれでしょう生物多様性(せいぶつたようせい)
A烏帽子島(えぼしじま)

烏帽子島(えぼしじま)は糸島市の無人島で、糸島半島と壱岐島(いきのしま)のほぼ中間に位置しています。鳥獣保護区(ちょうじゅうほごく)の特別保護(ほご)地区に指定されており、希少種であるカンムリウミスズメの繁殖(はんしょく)地として重要な島です。
福岡県内で一番魚の種類が多い川はどれでしょう生物多様性(せいぶつたようせい)
A筑後川(ちくごがわ)

筑後川(ちくごがわ)には約90種の魚がすんでいます。特に、一生を淡水(たんすい)でくらす 「純淡水魚(じゅんたんすいぎょ)」は、九州に41種が生息していますが、筑後川(ちくごがわ)にはなんとその8割(わり)以上の34種が生息しています。このほか、県内では矢部川(やべがわ)、那珂川(なかがわ)、遠賀川(おんががわ)、今川などにも多くの種類の魚がすんでいます。
現在、福岡県に定着*している外来種は何種いるでしょう(*継続(けいぞく)して子孫をつくることに成功している状態(じょうたい))生物多様性(せいぶつたようせい)
実際(じっさい)にいる植物は次のうちどれでしょう植物
A動くことができる

歩き回ることはできませんが、オジギソウのようにさわると葉を閉じる、フジのようにつるを動かして他の植物にからみつくなど、動くことができる植物がいます。
B虫を食べる

ハエトリソウやモウセンゴケなど、ハエやアリなどの小さな虫をとらえて食べる植物がいます。
C根や葉がほとんどない

マツバランのように、根も葉もほとんどない植物がいます。
D花がさかない

シダ植物は花をさかせず、葉のうらについた胞子(ほうし)で増えます。
実際(じっさい)にいる植物の名前は次のうちどれでしょう①植物
Q実際(じっさい)にいる植物の名前は次のうちどれでしょう②植物
実際(じっさい)にはいない植物の名前は次のうちどれでしょう植物
1月7日に七草がゆにして食べる植物を「春の七草」といいます。春の七草は次のうちどれでしょう植物
Q秋に楽しまれる代表的な草花を「秋の七草」といいます。秋の七草は次のうちどれでしょう植物
秋に楽しまれる代表的な草花を「秋の七草」といいます。秋の七草のうち、福岡県で絶滅(ぜつめつ)してしまった植物はどれでしょう植物
次のどんぐりの仲間のうち、落葉樹(らくようじゅ)はどれでしょう植物
福岡県内で絶滅(ぜつめつ)したほにゅう類は何種いるでしょうほにゅう類
鳥の祖先(そせん)は次のうちどれでしょう鳥類
Aほにゅう類
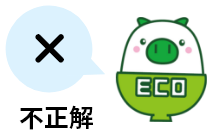
B恐竜(きょうりゅう)

鳥の祖先(そせん)は恐竜(きょうりゅう)です。最近の説では、ティラノサウルスなど二足歩行をしていた獣脚(じゅうきゃく)類のうち、一部のグループから鳥が進化したと考えられています。鳥と恐竜(きょうりゅう)にはたくさんの共通点があります。
鳥の行動として実際(じっさい)に確認されているのは次のうちどれでしょう鳥類
Aプレゼントをおくる

多くの鳥で見られる行動で、オスがメスの気を引くためにエサのプレゼントをおくります。カワセミやトビ、コアジサシなどが有名です。
B魚をとるためにエサをまく

サギの仲間のササゴイで観察されている行動です。水の表面に葉や昆虫(こんちゅう)、ゴミなどを投げ、それをエサだと思った魚がやってくるのを待ちぶせします。
Cエサを枝に串刺(くしざ)しにする

モズの仲間で見られる行動で、"はやにえ"といいます。はやにえを行う理由はよくわかっていません。
Dかたいエサを割(わ)るのに人を利用する

カラスで観察されている行動で、クルミのかたい殻(から)を割(わ)るために、道路にクルミをおいて車にひかせて割(わ)って食べます。
ツバメは冬には見られないけど、どうしているの?鳥類
A冬眠(とうみん)している
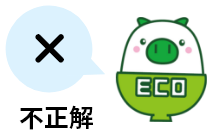
ツバメは冬眠(とうみん)をしません。あたたかい南の国ですごしています。ちなみに、鳥類で冬眠(とうみん)することがわかっているのは世界で1種だけです。
B巣の中でじっとかくれている
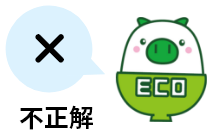
ツバメは冬はあたたかい南の国ですごしています。子育てに使った巣は、人間や他の動物がこわさなければ次の年までそのまま残っていますが、その中で冬をすごすことはしません。
C南の国ですごしている

秋の終わりになると南の国に飛んでいって、冬の間はあたたかい場所ですごします。ツバメはカやハエなどの小さな飛ぶ虫を食べるので、冬の日本はエサが取れないからです。春になると日本に帰ってきて子育てをします。このように、季節によってすむ場所を大きく変える鳥を渡り鳥いい、ツバメのように春~秋の間だけ日本にいる鳥を夏鳥といいます。
D夜行性になる
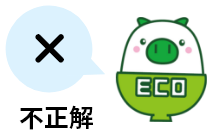
ツバメは一年中、昼間に活動します。冬はあたたかい南の国ですごしています。
福岡県にはドジョウの仲間は何種類くらしているでしょう魚類
コイの口ひげは何本あるでしょう魚類
Q世界共通の生きものの名前である学名に、久留米の名前がついている魚がいます。それは次のうちどれでしょう魚類
Aトラフグ
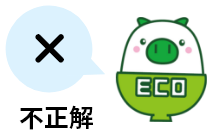
Bニッポンバラタナゴ

学名はRhodeus ocellatus kurumeusで、久留米市内の筑後川(ちくごがわ)でとられた個体から新種が報告(ほうこく)されたため、この学名がつきました。今では福岡県で絶滅危惧IB類(ぜつめつきぐ いちびーるい)に指定されるほど希少になってしまいました。
次の生きもののうち、昆虫(こんちゅう)はどれでしょう昆虫(こんちゅう)
Aダンゴムシ
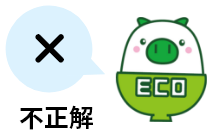
昆虫(こんちゅう)の最大の特ちょうは、脚(あし)が3対6本はえていることです。ダンゴムシは脚(あし)が7対14本あるので、昆虫(こんちゅう)ではありません。エビやカニに近い仲間です。
Bカメムシ

昆虫(こんちゅう)の最大の特ちょうは、脚(あし)が3対6本はえていることです。カメムシは脚(あし)が3対6本あるので昆虫(こんちゅう)です。
Cクモ
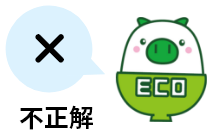
昆虫(こんちゅう)の最大の特ちょうは、脚(あし)が3対6本はえていることです。クモは脚(あし)が4対8本あるので、昆虫(こんちゅう)ではありません。ダニやサソリに近い仲間です。
Dサソリ
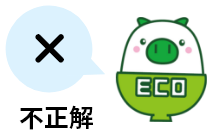
昆虫(こんちゅう)の最大の特ちょうは、脚(あし)が3対6本はえていることです。サソリは脚(あし)が4対8本あるので、昆虫(こんちゅう)ではありません。クモに近い仲間です。
カメの固い甲羅(こうら)は何でできているでしょうは虫類
カエルの前足の指は何本でしょう両生類
Q実際(じっさい)にいる昆虫(こんちゅう)の名前は次のうちどれでしょう昆虫(こんちゅう)
Aカンタン

バッタの仲間で、秋にルルルルと美しい声でなきます。漢字で邯鄲と書き、簡単(かんたん)とは関係ありません。
Bクビキリギス

バッタの仲間で、春先からジーーーという声でなきます。かみつく力が強く、はなそうとして体を強く引っぱっても首だけが残るほど、という理由からこの名前がつけられたといわれています。
Cドウガネブイブイ

コガネムシの仲間で、光沢(こうたく)のある茶色い体をしています。ドウガネは銅(どう)でできた鐘(かね)に色がにているのでつけられた名前ですが、ブイブイの由来はよくわかっていません。
Dミミズク

カメムシの仲間で、鳥のフクロウの仲間と名前が同じです。背中に耳のような突起(とっき)があるため、この名前がつけられました。
水生昆虫(こんちゅう)として有名なゲンゴロウですが、ゲンゴロウができないことは次のうちどれでしょう昆虫(こんちゅう)
A水中を泳ぐ
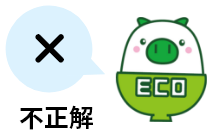
Bえらで呼吸(こきゅう)をする

ゲンゴロウは主に水中でくらしますが、えらはありません。呼吸(こきゅう)ははねと腹の間にたためた空気を用います。そのため時どき水面にあがってきて、ためた空気を交換(こうかん)します。
コオロギの耳は体のどこにあるでしょう昆虫(こんちゅう)
Q水路やため池の底でくらす二枚貝・イシガイ類は、生まれたすぐ後はどのようにして成長するでしょう貝類
A水底でプランクトンを食べてくらす
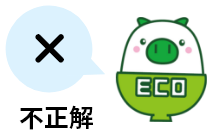
C魚のひれに付着し寄生(きせい)する

イシガイ類は福岡県ではゴツガイやカラスガイなどとよばれることもある大型の二枚貝で、親はアサリなどと同じように水中のプランクトンをえらでろ過(か)して食べます。しかし、生まれてしばらくは魚のひれに付着し寄生(きせい)して、養分をすって育ちます。しばらく成長すると親と同じ生活をするようになります。