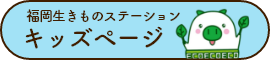リアルタイム生物季節
過去の記事
最新の記事
新しい年を迎え、1月5日から二十四節気の「小寒(しょうかん)」に入りました。これから寒さがいっそう厳しくなる時期です。外に出るのがついおっくうになりますが、冬ならではの姿を見せてくれる植物もあります。今回はその一つをご紹介します。
ヤドリギは、落葉広葉樹に寄生して育つ常緑小低木です。ふだんは寄生している木の葉に隠れて目立ちませんが、冬に葉が落ちると、緑の丸い塊のような姿がよく見えるようになります。日本ではあまり身近な植物ではありませんが、ヨーロッパではセイヨウヤドリギがクリスマス飾りに使われるなど、縁起の良い植物として親しまれています。
【2026年1月5日】
11月7日から二十四節気の「立冬」に入りました。
冬の気配が感じられる今日この頃ですが、里山では、コバノフジバカマやヒヨドリバナの花が寒空の下で見ごろを迎えています。これらの花の蜜は、渡りをする蝶として知られるアサギマダラの大好物。ちょうどこの時期、アサギマダラは暖かい場所を求めて南下しているところです。ふわふわと舞うアサギマダラの姿を見たら、そっと後を追いかけてみるとフジバカマやヒヨドリバナの花が見つかるかもしれません。
【2025年11月11日】
10月29日、福岡県保健環境研究所でキンモクセイの甘い香りが漂い始めました。昨年のリアルタイム生物季節では、同所で10月9日に開花したことを記事にしており、今年は20日ほど遅い開花となりました。
11月2日からは七十二候の「楓蔦黄(もみじつたきなり)」に入りました。保健環境研究所構内でも、イロハモミジが紅く色づき始め、ヤマノイモも黄色く染まり、秋の彩りが深まっています。朝晩の冷え込みも次第に厳しくなり、これから日を追うごとに景色が鮮やかに変化していくことでしょう。秋の深まりを感じながら、ぜひ紅葉狩りに出かけてみてはいかがでしょうか。
【2025年11月11日】
「秋分」は二十四節気の一つ。春分と同じく昼と夜の長さが同じになる頃で、秋分の日を始まりとする約2週間を指します。今年の秋分の日は9月23日でしたが、時をほぼ同じくして、秋の風物詩であるヒガンバナが咲き始めました。2021年から観察を続けている保健環境研究所近くの水田では、9月20日にヒガンバナの初開花が確認され、例年よりも1~2週間開花が遅かった昨シーズンと2日違いでした。朝晩の暑さが少しずつ和らいできたので、ヒガンバナもそれを感じ取って開花が始まったのでしょう*。 秋の過ごしやすい気候はこれから本番を迎えます。アウトドアなどで外に出かける際は、自然の中の秋の実りや花、紅葉にもぜひ目を向けてみてください。 *ヒガンバナ開花の仕組みについては、昨年度の「リアルタイム生物季節2024」を参考にしてください
【2025年9月26日】
9月2日から七十二侯の「禾乃登(こくものみのる)」、イネが実り始めるころ、に入っています。保健環境研究所の周辺の水田でも稲穂が色づき始めてきました。
新米を楽しみにしている方も多いと思いますが、穀物だけでなく、ぶどうや栗などの果実も旬を迎え、野山では木の実が色づき始めています。保健環境研究所構内でも、イチョウやホルトノキ、イロハモミジなどが今年もよく実っていて、秋の気配が深まってきました。また、今年はサンマも豊漁のようです。畑と山、海から届く豊かな実りに、みなさんも一足早い秋の訪れを感じてみてはいかがでしょうか。
【2025年9月5日】
猛暑日が続いていますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。7月28日から、七十二候の「土潤溽暑(つちうるおいてむしあつし)」に入り、暦上でも暑さが厳しい時期として表現される季節となっています。
夏真っ盛りのこの時期、屋外ではセミの大合唱が最盛期を迎え、水田では稲が青々と茂り、ウスバキトンボが群飛する夏らしい風情が広がっています。このウスバキトンボ、お盆シーズンを前に特に目立って増えることから、ご先祖様の生まれ変わりとして、別名「精霊とんぼ」と呼ばれてきました。他にも、水田周辺にはアカトンボ類やシオカラトンボなども飛んでいますので、暑い中ではありますが目を向けてみてはいかがでしょうか。
【2025年8月5日】
県内では、ここ1週間ほどで今シーズン初めてのセミの初鳴きが観察され始めています。保健環境研究所近郊では、6月26日にニイニイゼミ、7月1日にアブラゼミとヒグラシの今シーズン初めての鳴き声を確認しました。研究所では4年前からセミの初鳴きを記録していますが、今年は平年並みか少し遅めのようです。皆さんの地域はいかがでしょうか。
【2025年7月11日】
九州北部では、6月27日に梅雨明けが発表されました。6月中の梅雨明けは観測史上初めてで、昨年より20日、平年より22日も早く、梅雨期間はわずか19日間でした。
さて、あっという間に夏本番がやってきましたが、皆さんはこの夏をどんな風に楽しむ予定でしょうか。海水浴などで海に出かける方も多いと思いますが、砂浜ではハマゴウやツルナなどの海浜植物が小さな花を咲かせています。ビーチの絶景だけでなく、足元の自然にも少し目を向けてみると、新しい夏の発見があるかもしれませんよ。
【2025年7月11日】
6月8日、九州北部の梅雨入りが発表されました。昨年より9日早く、平年より4日遅い梅雨入りとなりました。
今年は梅雨入り早々に大雨となってしまいましたね。でも、外に出るとカエルの元気な合唱が聞こえたり、アジサイやクチナシの花がちょうど見ごろを迎えたりと、季節ならではの風景が広がっています。クチナシは、春のジンチョウゲや秋のキンモクセイと並ぶ「三大香木」のひとつで、甘くて濃厚な香りにはリラックス効果があるそうです。梅雨のじめじめした空気のせいで、なんとなく気分まで沈みがちですが、雨の合間に外へ出て、季節の移り変わりを感じてみるのもいいかもしれませんね。
*クチナシについては、当ホームページの「身近な生きもの図鑑」もご覧ください
【2025年6月13日】
5月は梅雨入り前の穏やかな気候が続き、さわやかな陽気を楽しめる時期ですが、先週から最高気温が25℃を超える暑い日が続いています。まだ体が暑さに慣れていない時期ですので、こまめに水分補給をするなど熱中症にお気をつけください。
さて、暦では、5月21日から二十四節気の「小満(しょうまん)」、あらゆる生命が満ち満ちていく頃、に入ります。福岡県保健環境研究所でも、スイカズラやハゼノキなど様々な花が咲き、クマバチやハナアブの仲間が飛び交っています。また、田植えや麦の収穫期を迎えることから、農業においても重要な時期とされています。生命の躍動を感じられるこの時期、周りの自然に目を向けてみてはいかがでしょうか。
【2025年5月22日】