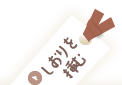ナガオカモノアラガイ
学名:Oxyloma hirasei (Pilsbry, 1901)Myしおりとは、あとでもう一度閲覧したい種の解説ページを保存し、いつでも見直すことができる機能です。このボタンを押すことで本解説ページをMyしおりページにブックマークし、Myしおりページへ移動します。
| 選定理由 | 県内での調査はやや不足しているが,産地は局地的で分断化している。かつて記録のあるいくつかの地域で近年の確認例がない。水域と陸域の境界であるエコトーン帯に生息する種で,圃場整備に伴う水路改修やため池改修の影響を受けやすく,今後も生息に適した環境が失われ続けていく可能性が高い。 |
|---|---|
| 危機要因 | 湖沼開発 河川開発 湿地開発 水路改修 農薬使用 |
| 分布情報 |
北九州市小倉南区,飯塚市,みやま市,那珂川市,篠栗町
MAP |
| 種の概要 | 殻長12mm。螺塔は小さく体層が極端に大きい。殻口は広く,殻は薄い。平野部の河川氾濫原,水田,ため池などの水際にある植生帯のエコトーンに生息する。塊状の卵を産む。早瀬(2008)による静岡県での調査では,本種は春と夏の2回繁殖し春型と夏型で寿命や形態が異なることが報告されている。国内では北海道から九州に分布。 |
| 生息環境 |
|