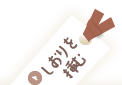ハイガイ
学名:Tegillarca granosa (Linnaeus, 1758)Myしおりとは、あとでもう一度閲覧したい種の解説ページを保存し、いつでも見直すことができる機能です。このボタンを押すことで本解説ページをMyしおりページにブックマークし、Myしおりページへ移動します。
| 選定理由 | 古い殻は県内各地でみられるが,生息が確認されているのは,大牟田市沿岸の限られた範囲のみである。有明海佐賀県沿岸には比較的多く生息していたが,2022年以降発生したサルボオの大量斃死以降はハイガイの生息地も大きく失われた可能性がある。大牟田市の生息地は2018年から2024年にかけての調査で近年も安定して生息していることが分かり,現在では本種の極めて重要な生息地のひとつ一つであると考えられる。曽根干潟(北九州市小倉南区)など周防灘の干潟域にも遺骸が多くみられ,近世まで生存していたと考えられるが,消滅時期は分かっていない。 |
|---|---|
| 危機要因 | 河川開発 海岸開発 水質汚濁 乱獲 産地局限 その他 |
| 分布情報 |
大牟田市,柳川市
MAP |
| 種の概要 | 殻長60mm,箱形,厚質,膨らみが強く,結節を備えた20本内外の放射肋があり,茶色い殻皮を被る。殻を焼いて「貝灰」を製造していたことが,和名の語源であるが,かつては柳川市沖端にも貝灰原料の本種の殻の山が存在した。有明海沿岸では「ししがい」「ちんみ」と呼ばれ,食用にされる。 |
| 生息環境 |
|