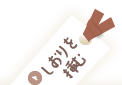ビョウブガイ
学名:Trisidos kiyonoi (Kuroda, 1929)Myしおりとは、あとでもう一度閲覧したい種の解説ページを保存し、いつでも見直すことができる機能です。このボタンを押すことで本解説ページをMyしおりページにブックマークし、Myしおりページへ移動します。
| 選定理由 | 本種はかつて博多湾・加布里湾などに多産したが,近年は摩耗した殻しかみつかっていないため,これらの産地では絶滅したと考えられる。玄界灘沿岸・響灘西部においては,新鮮な殻が確認され,生息している可能性が示唆された。曽根干潟の記録は詳細不明。いずれにしても,本種の個体群は大きく失わており,絶滅のおそれが高い状況にあるといえる。 |
|---|---|
| 危機要因 | 海岸開発 水質汚濁 産地局限 |
| 分布情報 |
北九州市小倉南区,福岡市西区,福津市,糸島市
MAP |
| 種の概要 | 日本では周防灘,響灘,玄界灘,天草沿岸の内湾域に分布するが,2000年代以降,生息が確実に確認されているのは熊本県天草市羊角湾(吉崎・山下, 2005)のみである。 Huber (2010)は学名の著者をMakiyama (1931)とするが,黒田(1929)でArca kiyonoi Makiyama (MS)を図示したために学名の著者はKuroda (1929)。 |
| 生息環境 |
|