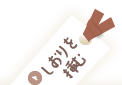オオアオホソゴミムシ
学名:Dendorocellus geniculatus (Klug, 1834)Myしおりとは、あとでもう一度閲覧したい種の解説ページを保存し、いつでも見直すことができる機能です。このボタンを押すことで本解説ページをMyしおりページにブックマークし、Myしおりページへ移動します。
| 選定理由 | 本種は野焼き草原のススキに依存する種で,県内では唯一,1986年に平尾台で記録されていた。その後2021年に平尾台で35年ぶりに再確認された。また,2023年度には,直射日光と,捕食者の目を避けて,主として薄暮と夜間に活動していること,平尾台での個体数は比較的多いことが解った。しかし,本種は広い野焼き草原に限ってみられる種で,県内で知られている生息地は平尾台が唯一なので,ランクを上げて今後とも注視していきたい。 |
|---|---|
| 危機要因 | その他 |
| 分布情報 |
北九州市小倉南区
MAP |
| 種の概要 | 体長9~10.5mm,頭と前胸が細長く,足が長いスマートなゴミムシで,背面は金属光沢の強い青錆色,足と触角は黄褐色。草原のススキに依存して生活しており,日中は根際や葉柄の中に潜み,黄昏から夜間に葉上の小昆虫などを捕食する。当初1種と考えられていた中から,林縁のススキ群落を利用する,より大型のモリアオホソゴミムシが発見され,区別されている。平尾台の草原の縁で行った灯火採集では2種同時に飛来した。草原縁の木陰になる株と,中央の日向の株とで2種がすみ分けている可能性がある。本州(栃木県以南),九州と国外では東南アジアに広く分布する。 |
| 生息環境 |
|