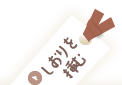サクラマス(ヤマメ)
学名:Oncorhynchus masou masou (Brevoort, 1856)Myしおりとは、あとでもう一度閲覧したい種の解説ページを保存し、いつでも見直すことができる機能です。このボタンを押すことで本解説ページをMyしおりページにブックマークし、Myしおりページへ移動します。
| 選定理由 | 県西部の高標高地には陸封型のヤマメが広く分布しているが,釣り目的で放流されたものがほとんどで,安定して繁殖している河川は限られる。また,かつて筑後川には降海型の個体群が存在していたことはほぼ間違いないが,すでに絶滅している。今後の気候変動の影響による流量減少や水温上昇が本種の絶滅の可能性を高めているほか,別亜種のサツキマス(アマゴ)や他地域産のサクラマス(ヤマメ)の放流による遺伝的攪乱も脅威である。 |
|---|---|
| 危機要因 | 河川開発 水質汚濁 気候変動 その他不法採集 乱獲 外来種侵入 |
| 分布情報 |
福岡市早良区,八女市,うきは市,朝倉市,糸島市,那珂川市,添田町 MAP |
| 種の概要 | 降海型のサクラマスでは体長600mm程度,陸封型のヤマメでは体長200mm程度。体はやや細く,茶色がかった銀白色。幼魚および陸封型では体側にパーマークと呼ばれる特徴的な青灰色の楕円形斑紋が並ぶ。口は大きい。河川の渓流域から上流域の,夏季でも水温が20℃を超えない瀬淵構造が明瞭な環境に生息する。繁殖期は晩秋で,砂礫底に穴を掘って産卵する。降海型のサクラマスは海域で成長した後,春に川を遡上して,秋の産卵期までを川で過ごす。 |
| 特記事項 | ― |
| 生息環境 |
|