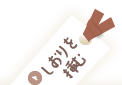ニホンウナギ
学名:Anguilla japonica Temminck & Schlegel, 1846Myしおりとは、あとでもう一度閲覧したい種の解説ページを保存し、いつでも見直すことができる機能です。このボタンを押すことで本解説ページをMyしおりページにブックマークし、Myしおりページへ移動します。
| 選定理由 | 県内全域に分布するが,河川,水路などの開発に伴う生息条件の悪化,気候変動に伴う海流環境の変化,乱獲といった減少要因によって,既知のすべての個体群で危機的水準まで減少している。県内では養鰻種苗確保のためのシラスウナギ漁が行われている河川は多くはないために全県的な乱獲状態がみられるとはいえないが,本種は産卵場所を同一とする単一個体群であり,県外の生息状況の影響を受ける。 |
|---|---|
| 危機要因 | 湖沼開発 河川開発 海岸開発 ダム建設 水路改修 農薬使用 気候変動 乱獲 |
| 分布情報 |
県内ほぼ全水系,海域
|
| 種の概要 | 最大約1m,通常約70cm。体は長い円筒形で,背面は暗色,腹面は一般に白から黄色。成熟期(銀ウナギ)に達すると腹面まで黒っぽくなり,体側の銀色が目立つようになる。海や川,水路,池沼といったあらゆる環境に生息する。夜行性で,昼間は石や植生の隙間や砂泥中に隠れる。 |
| 特記事項 | ― |
| 生息環境 |
|