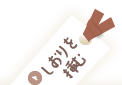クルメサヨリ
学名:Hyporhamphus intermedius (Cantor, 1842)Myしおりとは、あとでもう一度閲覧したい種の解説ページを保存し、いつでも見直すことができる機能です。このボタンを押すことで本解説ページをMyしおりページにブックマークし、Myしおりページへ移動します。
| 選定理由 | 日本海側では1980年代までに絶滅した。現在は筑後川・矢部川の河口域を中心に生息が確認されているが,安定して繁殖しているのは筑後川の感潮域のみと思われる。筑後川では2021年の調査では少なくない個体が確認されたものの,同地における生活史に関する知見が少なく,浚渫や護岸改修などの影響で予期せぬ形で絶滅する可能性があることから,注意が必要である。 |
|---|---|
| 危機要因 | 河川開発 海岸開発 湿地開発 |
| 分布情報 |
久留米市,柳川市,大川市
MAP |
| 種の概要 | 体長250mm。体は細く円筒形で,下顎が長く伸びる。体は銀白色で,下顎の下面は黒色。汽水性種で,低塩分の湖沼や河川感潮域に生息する。繁殖期は春から夏にかけてで,筑後川では河川感潮域上端部の水面において夜間に産卵行動を行う様子が観察されている。卵には粘着性のある糸が備わっており,植物片などに付着して発生する。 |
| 特記事項 | ― |
| 生息環境 |
|