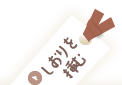ホウロクシギ
学名:Numenius madagascariensis (Linnaeus, 1766)Myしおりとは、あとでもう一度閲覧したい種の解説ページを保存し、いつでも見直すことができる機能です。このボタンを押すことで本解説ページをMyしおりページにブックマークし、Myしおりページへ移動します。
| 選定理由 | 曽根干潟,瑞梅寺川河口,和白干潟など広い干潟に飛来するが,近年減少が著しい。特に曽根干潟では2000年代前半頃には50羽を超える飛来がみられたものの,近年は10羽を超えることは少なくなり,2010年頃との比較でも60%以上の減少となっている。餌生物の減少などの生息環境悪化に伴う渡りルートの変化や気候変動などによる個体群縮小の影響を受けている可能性がある。世界的に絶滅危機の認識が高まっており,IUCNレッドリストでは減少率の大きさからENとされている。 |
|---|---|
| 危機要因 | 海岸開発 気候変動 その他 |
| 分布情報 |
北九州市小倉南区,福岡市東区,福岡市西区,大牟田市,行橋市,豊前市,福津市,糸島市,芦屋町,岡垣町,遠賀町,苅田町,吉富町
MAP |
| 種の概要 | 全長53~66cm。全身が淡いバフ色で,全身に細かい黒褐色の縦斑がある。嘴は顕著に長く,下に反る。ダイシャクシギに似るが,ダイシャクシギは下腹部や腰が白いという点で区別できる。繁殖地は東シベリアからカムチャッカにかけてで,冬は主にオーストラリアで越冬する。日本では春秋の渡りの時期に通過して行く。泥質干潟などでゴカイ類やカニを食べる(環境省,2014)。 |
| 特記事項 | カテゴリー判定基準:A2,B1・3,D |
| 生息環境 |
|