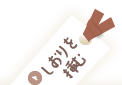サンショウクイ
学名:Pericrocotus divaricatus (Raffles, 1822)Myしおりとは、あとでもう一度閲覧したい種の解説ページを保存し、いつでも見直すことができる機能です。このボタンを押すことで本解説ページをMyしおりページにブックマークし、Myしおりページへ移動します。
| 選定理由 | 県内では,1980年代までは繁殖が確認されていたが,1990年代以降,繁殖期の確認情報がない。全国的に繁殖場所での確認例は減っているが,生息環境である森林の状況が変化していない場所で生息状況が悪化していることから,餌となる昆虫類の減少や越冬地での森林伐採が影響しているともいわれている。県内においては生息適地となるアカマツ林や落葉広葉樹林の減少も一因と考えられる。 |
|---|---|
| 危機要因 | 気候変動 遷移進行 植生変化 その他 |
| 分布情報 |
北九州市門司区,北九州市若松区,北九州市小倉北区,北九州市小倉南区,福岡市東区,福岡市博多区,福岡市中央区,福岡市南区,福岡市西区,福岡市城南区,直方市,飯塚市,田川市,柳川市,八女市,小郡市,筑紫野市,春日市,大野城市,宗像市,福津市,宮若市,糸島市,那珂川市,篠栗町,新宮町,芦屋町,水巻町,岡垣町,小竹町,鞍手町,糸田町,苅田町
MAP |
| 種の概要 | 全長約20cm。体は細く尾は長め,雄の額から頭部は白く,後頭,後頸,過眼線は黒い。背,肩羽,腰,上尾筒は青灰色で,下面全体は白色で脇は灰色を帯びる。本種は,中国東北部,朝鮮半島,本州,四国,九州に夏鳥として飛来し,東南アジアで越冬する。平地や山地の大きな落葉樹のある樹林にすむ。樹冠で昆虫類を採食する。1980年代以降全国各地で急速に生息状況が悪化し,生息が確認できなくなった場所が多い(環境省,2014)。 |
| 特記事項 | カテゴリー判定基準:①②,D。春秋には渡り途中のものが県内各地で比較的普通に観察される。近縁種リュウキュウサンショウクイ(P. tegimae)が近年西日本に生息を拡大,増加しており,県内でも普通にみられるようになっている。 |
| 生息環境 |
|