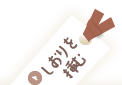オオキンブナ
学名:Carassius buergeri buergeri Temminck & Schlegel, 1846Myしおりとは、あとでもう一度閲覧したい種の解説ページを保存し、いつでも見直すことができる機能です。このボタンを押すことで本解説ページをMyしおりページにブックマークし、Myしおりページへ移動します。
| 選定理由 | 県内では7水系から生息情報があるが,生息地は限られ個体数も少ない。生息地でも小型の個体がほとんど採集されないことから,繁殖に適した環境が失われつつあることで,再生産に支障が出ているものと考えられる。また,放流された国外外来種のキンギョC. auratusや国内外来種のゲンゴロウブナとの競合・交雑による影響を受けている可能性もあり,今回カテゴリーを変更した。 |
|---|---|
| 危機要因 | 河川開発 水路改修 外来種侵入 競合種拡大 |
| 分布情報 |
久留米市,直方市,柳川市,古賀市,糸島市,那珂川市,上毛町
MAP |
| 種の概要 | 体長300mm。体高はやや低く,背鰭分枝軟条数は14~16。体色は黄色味が強い。2倍体で両性生殖を行う。河川の中下流域や平地の水路などに生息する。繁殖期は春で,岸際の抽水植物帯でばらまき型の産卵をする。雑食性。九州産在来フナ類の分類体系については不明な点も残るが,今回は上記の形態的特徴に当てはまるものを本種として評価した。 |
| 特記事項 | ― |
| 生息環境 |
|