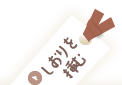ミユビシギ
学名:Calidris alba (Pallas, 1764)Myしおりとは、あとでもう一度閲覧したい種の解説ページを保存し、いつでも見直すことができる機能です。このボタンを押すことで本解説ページをMyしおりページにブックマークし、Myしおりページへ移動します。
| 選定理由 | 主に冬鳥として砂浜海岸や砂質の干潟に飛来する。博多湾では100羽を超える群れが越冬しているほか,玄界灘および響灘沿岸の砂浜では数十羽程度の小群が越冬している。周防灘や有明海では稀にみられるだけで,定期的な飛来地はみられない。県内の飛来数は200羽前後と推定される。ほかのシギ類と比較すると減少率は小さいが,徐々に減少している。飛来地の生息環境は維持されており,餌生物の減少や個体群そのものの縮小が影響していると考えられる。 |
|---|---|
| 危機要因 | 海岸開発 気候変動 その他 |
| 分布情報 |
北九州市若松区,北九州市小倉南区,福岡市東区,福岡市西区,行橋市,宗像市,古賀市,福津市,新宮町,芦屋町,岡垣町,吉富町
MAP |
| 種の概要 | 全長20~21cm。嘴と足が短い小型のシギ。夏羽は頭から胸にかけて茶褐色で縞がある。冬羽は背面は灰白色,下面は白色となる。嘴と足は黒色。北極海に面する半島や島嶼が繁殖地。越冬地は北半球低緯度地域から南半球まで広く分布(樋口ら,1996)。日本には旅鳥として全国に現れ,本州以南では少数が越冬する(中村・中村,1995b)。海岸の砂浜を好んで生息,波打ち際で波に合わせて走り,小さな甲殻類,貝類,ゴカイ類などを食べる(樋口ら,1996)。 |
| 特記事項 | カテゴリー判定基準:A2,D |
| 生息環境 |
|