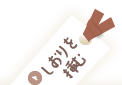タマシギ
学名:Rostratula benghalensis (Linnaeus, 1758)Myしおりとは、あとでもう一度閲覧したい種の解説ページを保存し、いつでも見直すことができる機能です。このボタンを押すことで本解説ページをMyしおりページにブックマークし、Myしおりページへ移動します。
| 選定理由 | 県内には留鳥として各地の平野部の水田地帯に生息する。営巣環境は稲田,ハス田,休耕田などの水田環境で,ため池や遊水池などの湿地環境ではほとんどみられない。非繁殖期には水路や河川などに移動して越冬する。生息数は1,000個体未満と推定される。まとまった面積の水田地帯には生息しているが,二毛作の進んでいる地域では田に水が入る時期が遅くなるため,繁殖しなくなった場所も多い。急速な農業の変化に適応できず,個体数を減らしていると考えられる。 |
|---|---|
| 危機要因 | 水路改修 農薬使用 乾田化 その他 |
| 分布情報 |
北九州市若松区,北九州市小倉南区,福岡市西区,福岡市早良区,久留米市,飯塚市,田川市,柳川市,行橋市,小郡市,筑紫野市,宗像市,古賀市,福津市,うきは市,宮若市,嘉麻市,みやま市,糸島市,篠栗町,志免町,岡垣町,遠賀町,小竹町,鞍手町,筑前町,大刀洗町,みやこ町,上毛町
MAP |
| 種の概要 | 全長約25cm。先端が下に曲がっている長い嘴にずんぐりした体形のシギ。雌の方が色彩が鮮明。目の周囲の白色部はまが玉状に後頭に伸びる。中国,東南アジア,インド,アフリカなどに留鳥として生息する。国内では主に本州中部以南に留鳥として生息する。主に湿原,水田,河川,池沼などのある程度植生のある湿地を好む。一夫多妻制。湿地の植生のある部分に皿状の巣を作る。貝類,環形動物,甲殻類,昆虫類,種子などを食べる(環境省,2014)。 |
| 特記事項 | カテゴリー判定基準:A2,D |
| 生息環境 |
|