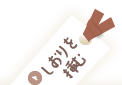ブナシメジ
学名:Hypsizygus marmoreusu (Peck) H.E.GigelowMyしおりとは、あとでもう一度閲覧したい種の解説ページを保存し、いつでも見直すことができる機能です。このボタンを押すことで本解説ページをMyしおりページにブックマークし、Myしおりページへ移動します。
| 選定理由 | 従来生息地は英彦山,犬ヶ岳,御前岳,宝満山,脊振山,九千部山のブナ林の立ち木,倒木などであったが,英彦山,犬ヶ岳では確認されなくなってきている。ほかの地域でも確認が困難になってきており,今後もシカによる被陰植物の食害の拡大やブナ林の衰退による本菌の絶滅が危惧される。 |
|---|---|
| 危機要因 | 気候変動 シカ増加 産地局限 |
| 分布情報 |
*八女市,*豊前市,*太宰府市,*那珂川市,*添田町
MAP |
| 種の概要 | 主に晩秋に,ブナの生立木,立ち枯れ木,倒木に発生する食用きのこで人工栽培も行われ,いわゆるしめじとして販売されている。幼菌では灰色~灰褐色であるが,成菌では白~灰色の傘の中心部に大理石模様を有することが特徴で,独特の粉臭がする。柄もひだも白色で単生することが多くて集団発生はなく,子実体を見つけることは比較的困難である。 |
| 特記事項 | ― |
| 生息環境 |
|