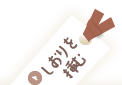オオバミヤマノコギリシダ
学名:Diplazium hayatamae N.Ohta et M.TakamiyaMyしおりとは、あとでもう一度閲覧したい種の解説ページを保存し、いつでも見直すことができる機能です。このボタンを押すことで本解説ページをMyしおりページにブックマークし、Myしおりページへ移動します。
| 選定理由 | RDB2001では那珂川市に県内唯一の自生地があるとされていたが,今回の調査ではこのほかに久留米市,飯塚市,筑紫野市で新たに計122株の現存を確認した。生育環境はいずれもスギ・ヒノキ植林地であり,久留米市と筑紫野市には各1株が生育するが,飯塚市では約120株が30mほどの範囲に群生している。本種もコクモウクジャクなどと同様に分布を北上させていると考えられ,別の場所でも発見される可能性が高いため,カテゴリーを見直した。 |
|---|---|
| 危機要因 | 森林伐採 |
| 分布情報 |
久留米市,飯塚市,筑紫野市,*那珂川市
MAP |
| 種の概要 | 山地の林床に生育する常緑性のシダ植物。根茎は長く匍匐し,やや狭い間隔で葉をつける。外観がミヤマノコギリシダに類似するが,本種はヒロハノコギリシダに近縁な種であり,葉はより大型である。なお,飯塚市(上記とは別の産地)と新宮町には本種とミヤマノコギリシダの雑種のみが群生している場所も存在するため,同定の際には注意が必要である。雑種の場合,葉質はより薄く,胞子は不斉になる。 |
| 生息環境 |
|