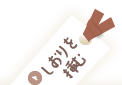ツツイイワヘゴ
学名:Dryopteris tsutsuiana Sa.KurataMyしおりとは、あとでもう一度閲覧したい種の解説ページを保存し、いつでも見直すことができる機能です。このボタンを押すことで本解説ページをMyしおりページにブックマークし、Myしおりページへ移動します。
| 選定理由 | 豊前市(基準産地)と八女市の各1か所のみに現存する。1960年代の発見当初,基準産地には約50株生育していたが,1980年代の砂防ダム建設と林道工事に誘発された土石流により大部分の個体が消失した。RDB2001では12株のみ生育していたが,その後シカ食害が進行して絶滅状態となった。今回の調査で1株の幼若個体が同産地に現存することを確認し,防鹿柵を設置しモニタリングしている(金光,2022)。八女市の自生地は2024年に新たに発見されたが,現存個体は4株と少なく,保護対策の検討が必要である(金光,2024)。 |
|---|---|
| 危機要因 | 森林伐採 土地造成 シカ増加 産地局限 |
| 分布情報 |
八女市,豊前市
MAP |
| 種の概要 | 山地の林床に生育する常緑性のシダ植物。根茎は斜上し,葉柄の下部には黒褐色の鱗片を密につける。外観はイワヘゴやツクシオオクジャクにやや類似するが,本種の葉脈はやや凹む点,ソーラスが辺縁からやや内側の位置につく点が異なる。3倍体と2倍体の型が存在し,2倍体の型はヤマエオオクジャクと仮称されており熊本県に分布する。八女市の個体群も2倍体型の可能性が指摘されている(金光,2024)。日本固有種で豊前市が基準産地。築上町にも分布するとされていたが,当産地の標本はクマイワヘゴに見直された。 |
| 生息環境 |
|