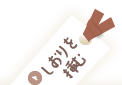ミヤマイタチシダ
学名:Dryopteris sabaei (Franch. et Sav.) C.Chr.Myしおりとは、あとでもう一度閲覧したい種の解説ページを保存し、いつでも見直すことができる機能です。このボタンを押すことで本解説ページをMyしおりページにブックマークし、Myしおりページへ移動します。
| 選定理由 | 糸島市の1か所に標本産地があり,RDB2001では1株のみ確認されていた。その後,2018年に同山地の別地点において231株が生育する群生地が新たに発見されており(金光,2019),今回の調査ではほかの地点も合わせて合計248株の現存を確認した。本県は九州本土における本種の唯一の産地であるほか,群生地以外では数個体が現存するに過ぎず,アカガシ林の発達により被陰が進行して小型化している場所も存在する。 |
|---|---|
| 危機要因 | 気候変動 遷移進行 産地局限 |
| 分布情報 |
糸島市
MAP |
| 種の概要 | 山地の林床に生育する常緑または夏緑性のシダ植物。根茎は斜上し,葉柄の下部には幅広い鱗片を密につける。外観はナガバノイタチシダに若干類似するが,葉脈が明瞭に凹むほか葉にはやや光沢がある点で識別は容易である。また,本種のソーラスは葉身の上側半分程度につき,ソーラスがついた部分の葉はやや萎縮する。国内では,北海道~九州に分布する。 |
| 生息環境 |
|