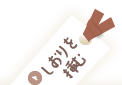タキミシダ
学名:Antrophyum obovatum BakerMyしおりとは、あとでもう一度閲覧したい種の解説ページを保存し、いつでも見直すことができる機能です。このボタンを押すことで本解説ページをMyしおりページにブックマークし、Myしおりページへ移動します。
| 選定理由 | 福岡市早良区,那珂川市,篠栗町,宮若市に計4か所の産地があり,篠栗町以外の自生地は1960年代の確認情報を最後に絶滅状態となっていた。今回の調査で,福岡市早良区の2か所のスギ植林内で合計27株が現存する自生地を発見したためカテゴリーを変更した。実葉をつけた成熟個体は多いものの個体群が小規模なため,森林伐採による環境変化や盗掘により容易に絶滅するおそれがある。このほか,那珂川市に1株が現存するとの情報がある。 |
|---|---|
| 危機要因 | 森林伐採 園芸採取 |
| 分布情報 |
福岡市早良区,*那珂川市
MAP |
| 種の概要 | 山地渓谷の岩壁などに着生する常緑性のシダ植物。葉の裏面の脈上に線状のソーラスを多数つけることが特徴である。生育環境の選好性が強く,成長速度も遅いため,移植や栽培が一般的に困難とされる。独立配偶体を形成することが知られており,胞子体が消失した自生地においても前葉体が生存している可能性がある。本種の配偶体は無性芽を多数つけて旺盛に増殖するが,胞子体は特定の条件にならなければ発生しないようである。 |
| 生息環境 |
|