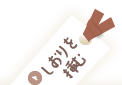カワラマンネングサ
学名:Sedum kawaraense Takuro Ito & KanemitsuMyしおりとは、あとでもう一度閲覧したい種の解説ページを保存し、いつでも見直すことができる機能です。このボタンを押すことで本解説ページをMyしおりページにブックマークし、Myしおりページへ移動します。
| 選定理由 | 香春町およびみやこ町の石灰岩地に局在し,今回の調査では1,820株の現存を確認した。個体数は多いが,自生地は数地点に限られ,石灰岩上に局在する。自生地周辺では石灰採掘が盛んであり,本種は継続的な減少傾向にあると推定される。また,本種は近縁他種のようにシュートから発根して増殖しないことから個体ごと盗掘される可能性が高く,越年草で種子繁殖に依存的であることから盗掘による影響を強く受けることも懸念される。 |
|---|---|
| 危機要因 | 石灰採掘 園芸採取 乱獲 産地局限 |
| 分布情報 |
香春町,みやこ町
MAP |
| 種の概要 | 2015年に発見され1),2023年に伊東ほか(Ito et al.,2023)によって記載された新種である。石灰岩生の越年草で,ロゼットで越冬する。ロゼット葉はへら型で互生,1~2cm。茎は基部で分枝して1~数本,高さ2~8cmほど,しばしば赤みを帯びる。茎からは普通発根せず,無花のシュートは出さない。茎葉はへら形~倒披針形で互生,5~6月上旬頃に開花する。花弁は黄色で5個,披針形で4.5~6.5mm。心皮は5個。葯は赤色。日本固有種で現在のところ分布が知られているのは福岡県のみ。 |
| 特記事項 | 1)発見者は本分科会の金光浩伸委員である。 |
| 生息環境 |
|