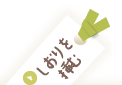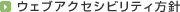脊振山の自然林
Myしおりとは、あとでもう一度閲覧したい種の解説ページを保存し、いつでも見直すことができる機能です。このボタンを押すことで本解説ページをMyしおりページにブックマークし、Myしおりページへ移動します。
| 群落の特徴 | 脊振山地の主稜線から,標高800を下限として,断続的にブナ群落が残存している。これらのブナ林は二次植生から回復した自然林と思われるが,一部に胸高直径50cm前後の個体群をもつ立派な林分もある。尾根を下がると次第にアカガシの混在が認められる。アカガシ林は標高900の尾根筋から500付近まで認められ,下限付近では大部分が伐採により撹乱されており,シイ・カシ萌芽林的な林相となっている。尾根筋ではブナ群落と交錯しながら小さな林分が点在している。鬼ヶ鼻付近では純群落状の良好な林分が認められる。 ブナ群落の周辺は,かなり広範囲にアカシデ-イヌシデ群落が展開している。このほか,リョウブ低木林およびミヤコザサ草原などがある。ミヤコザサ草原は20~30年前には残存ブナ林の周辺部で広大な面積を占めていたが,現在はかなりの部分でブナ,リョウブ,コバノミツバツツジ,ネジキなどを主とした幼木林化しており,遷移が進行しつつある。 尾根筋に近い急斜面の岩場にはツクシシャクナゲ個体群も見られる。 |
|---|---|
| 構成群落 | ☆ブナ群落(E),☆アカガシ群落(E・H),☆アカシデ-イヌシデ群落(A),リョウブ低木林,ミヤコザサ群落,ツクシシャクナゲ個体群 |
| 群落立地 | 当該地域は,福岡・佐賀両県の県境をなす。東端の九千部山(標高847)から始まり,主峰脊振山(1055)から北西へ延びる主尾根は,標高900~800を維持しながら金山(967)へと続き,三瀬峠(583)へ至り,更に井原山(983),雷山(955)を経て羽金山(900),浮岳(805)から西端の十坊山(535)へ至る。これらの山地の地質は中生代末の花崗岩類が基盤を作っているが,脊振山頂付近は三郡変成岩類となっている。地形は南西側は緩斜面,北東側は急斜面であり,福岡県側は一般に深く切り込まれた谷が発達している。 |
| 群落評価 | B(福岡県) |